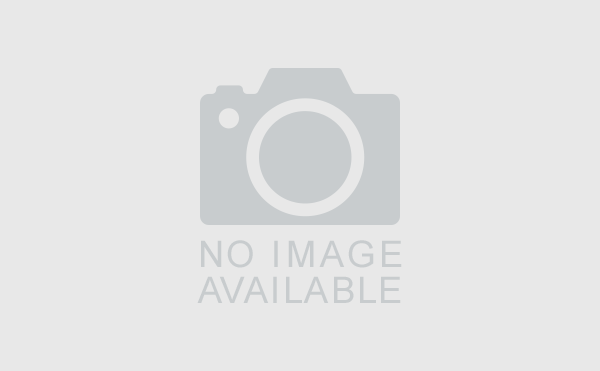早朝から哲学の道へ、そして大原へ(1)
8日は早朝から哲学の道へ、そしてその後、大原へ行ってきました。
哲学の道は桜の名所としてよく知られた場所です。満開の時期は平日でもかなりの混雑になりますが、7時前ぐらいの時間であればさすがにまだ観光のお客さんは少なく、桜ほ見ながらゆっくり歩くことができます。ここ何年かよくこの形で早朝にでかけています。
自宅から哲学の道までは車で40分程度です。で、白沙山荘の隣の駐車場に車をいれます。だいたい1時間500円ぐらい。このあたりが哲学の道の一番北になります。東西の通りでいうと今出川通り。すぐ近くにラーメンのますたに本店があります。赤い屋根の小汚い(失礼・・)ラーメン屋さんですが、ここのラーメンは好み。今回はスルーです。
このあたりが哲学の道のスタート地点。桜はほぼ満開です。もうちよっと時期が遅いとこのあたりは水路が花びらでいっぱいになります。奥の方から手前に向けての流れで手前に花びらがたまります。

なにか編笠をかぶった方がいました。このあたりでは早朝、中国からの方がウェディング写真を撮っていることがありますが、今回は出会いませんでした。
日本のこの桜の時期に来てウエディングフォトを撮るというのが中国の方にはステータスのようです。コロナの時期はさすがに来ている方は見かけませんでしたが、最近、また戻ってますね。蹴上のイングラインのあたりでも見かけます。

風がなく水面が静かで天気もよいので、水路にきれいに桜が映り込んでいます。こういう時は珍しいかも。
ベタな写真ですが、編笠氏もちょっと映り込んでいい感じ。尺八でも吹いて歩いてほしいところ。それは虚無僧、かぶるものも違うか・・。


木とか場所によって咲き方が違いますが、ほぼ満開の状態です。
この一斉に花が開く様子というのは、やはりなにか「危うさ」のようなものも感じるところがあります。
「桜の樹の下には死体が埋まっている」と書いたのは坂口安吾でしたか。違う、梶井基次郎か。梶井基次郎といえば「檸檬」。今も京都の丸善に行くと「檸檬」の本とスタンプがおいてあります。あ、話がそれた。
あと、思い出すのは坂口安吾の「桜の森の満開の下」と、それをもとにした野田秀樹の「贋作 桜の森の満開の下」。野田さんの脚本の芝居はリアルで2回見ています。違うキャストでの公演。ラストの桜がバーッと舞い散るシーンは印象的。大好きな芝居です。

桜はやはりこんな逆光の感じで撮るのが基本かな。

すぐ近くが銀閣で、そこから山の方へ行くと大文字の火床に行けます。紅葉の名所の永観堂も近いです。ということで、時間がたつにつれてどんどん人が増えます。やはり外国の方が多いです。ただ、7時前はまだすいていますし、あたりの駐車場も入れられますのでおすすめです。

古い中華料理のお店。ここは入ったことないなー。

現金だけね。さもありなん。

さて、メインの南北の水路沿いの道まで出てきました。ここから南へ進み、とりあえず南端の若王子神社まで行きます。

つづく。