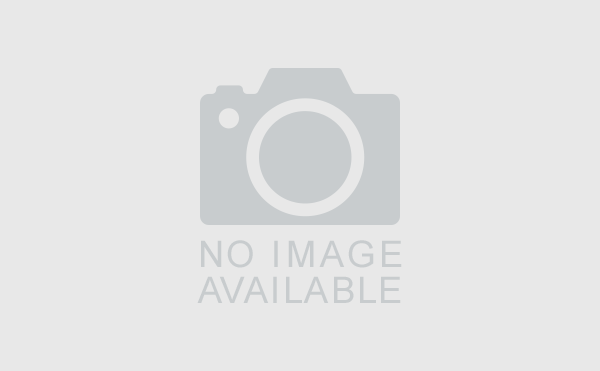6040日本スキー場開発 その可能性と限界、課題(2)
こちらに日本スキー場開発関連の各スキー場のリフト券販売数の月次情報が開示されています。
少し下へスクロールするとグリーンシーズンの状況も開示されています。これを見ると全般に販売数は前年を上回っているところがほとんどで相応に堅調に推移していることが見て取れます。
スキー場の方は当然積雪量によって営業可能な日数が変わってきます。昨年は12月から比較的まとまった降雪があり全般に降雪量が多かったため営業日を多く取れたという影響もプラスに作用しています。春に白馬に行きましたが、積雪量が多いことによる枝折れや倒木などの雪害がかなり見られました。こんなことは印象としては初めてです。
逆に言えば、降雪が少ない暖冬の年は営業日数が少なくなり、業績にはマイナスに作用することもあるということになります。
気候の方は傾向としては温暖化ということが言われ、実際、夏の暑さはもう酷暑というところも多いです。となると、全体には降雪量も減少傾向となる可能性が高そうに思われますが、必ずしもそうとも言えない面もあります。海水温が高いと水蒸気の発生量も多くなり、その分、雲の発生とそれに伴う降雪量が増加し、短期間に一気に降雪があるドカ雪が増えるという指摘もあるようです。
人工降雪機の設備なども整えてはいるようですが、やはり自然条件、気象の状況によって営業の環境が大きな影響を受けることはしょうがないところです。
もう一点の注目ポイントはグリーンシーズンです。
「スキー場」ですから営業の中心はウィンターシーズンということになりますが、夏もスキー場のゴンドラを動かしてトレッキングや登山のお客さんなどに利用してもらうということは以前からされていました。
栂池であれば、ゴンドラの頂上の先には栂池自然園があり、気軽に木道などを歩いて高山植物などを見ることができます。岩岳はユリ園をつくったり、スキー場のコースをMTBやバギーでも走れるようにしていましたし、八方尾根はゴンドラの先から八方池や唐松岳の方へ行けるルートが整備されています。いずれもわりと手軽に自然を楽しめるよいところですが、やはり集客力は冬場ほどではありませんでした。
この中で新たな集客に成功したのが岩岳です。ここは白馬連山の手前の山で、そのため頂上付近からは白馬連山が目前に迫る絶景が楽しめます。ここに展望デッキやカフェ、ブランコなどをつくり、様々なアクティビティなども拡張し、従来からのMTBやバギーなどだけでない展開をはかりました。逆に以前からあったユリ園はなくなっています。
これで一気にお客さんが増え、ほぼ冬場に匹敵するだけのお客さんが来るようになりました。岩岳は今年からは新設された新しいゴンドラも稼働しています。白馬地域は従来からオーストラリアなどからのインバウンド需要があり、それは現在も継続しています。コロナの時期から一気に観光客数も戻り、時期によってははオーバーツーリズムの弊害が生じるような状況もあるようです。というように、昔のような国内スキー・スノボブームのようなことはないものの、全般には活況を呈する状況となっており、この地域は夏場の観光も含めてその評価を高めてきています。
ただ、今後についてはそう楽観できない課題もあります。
つづく。